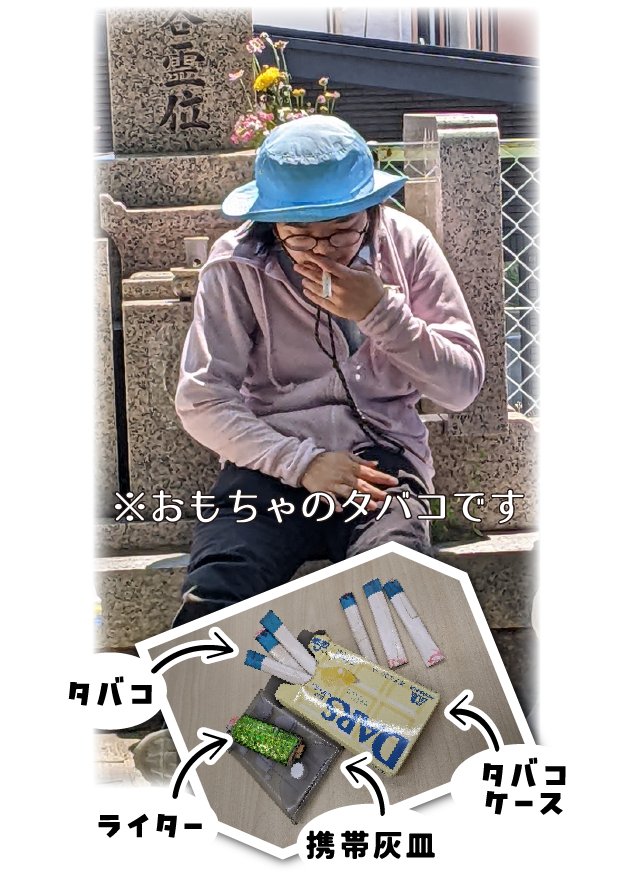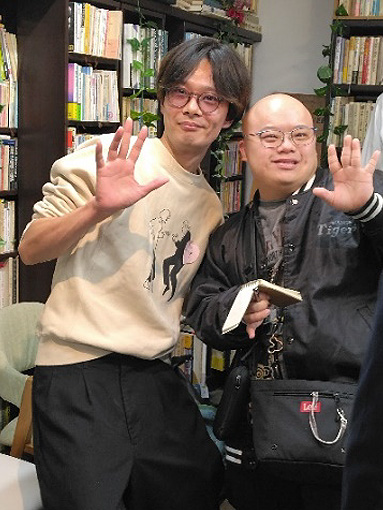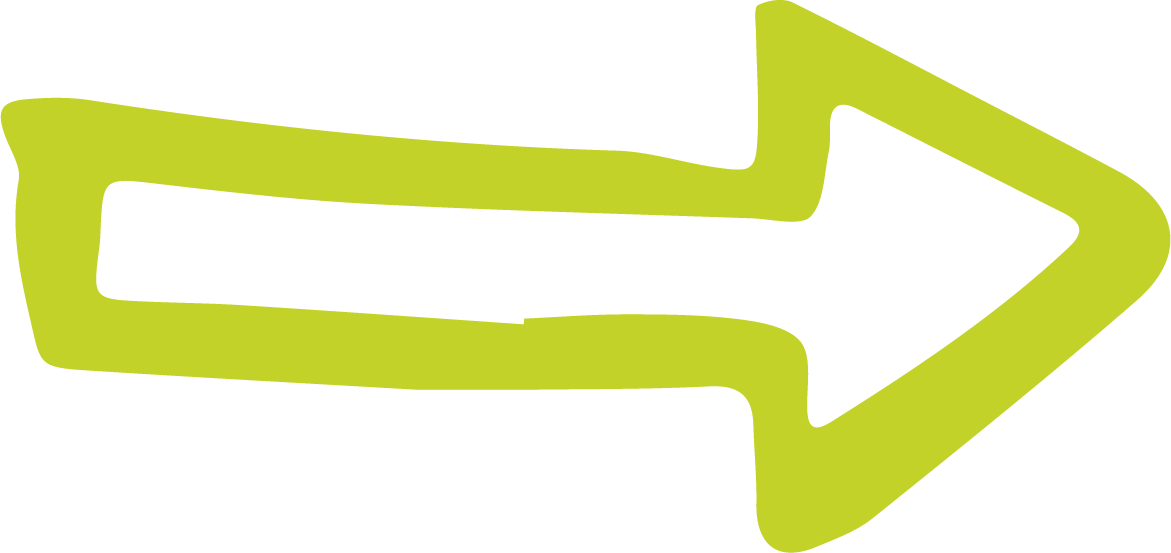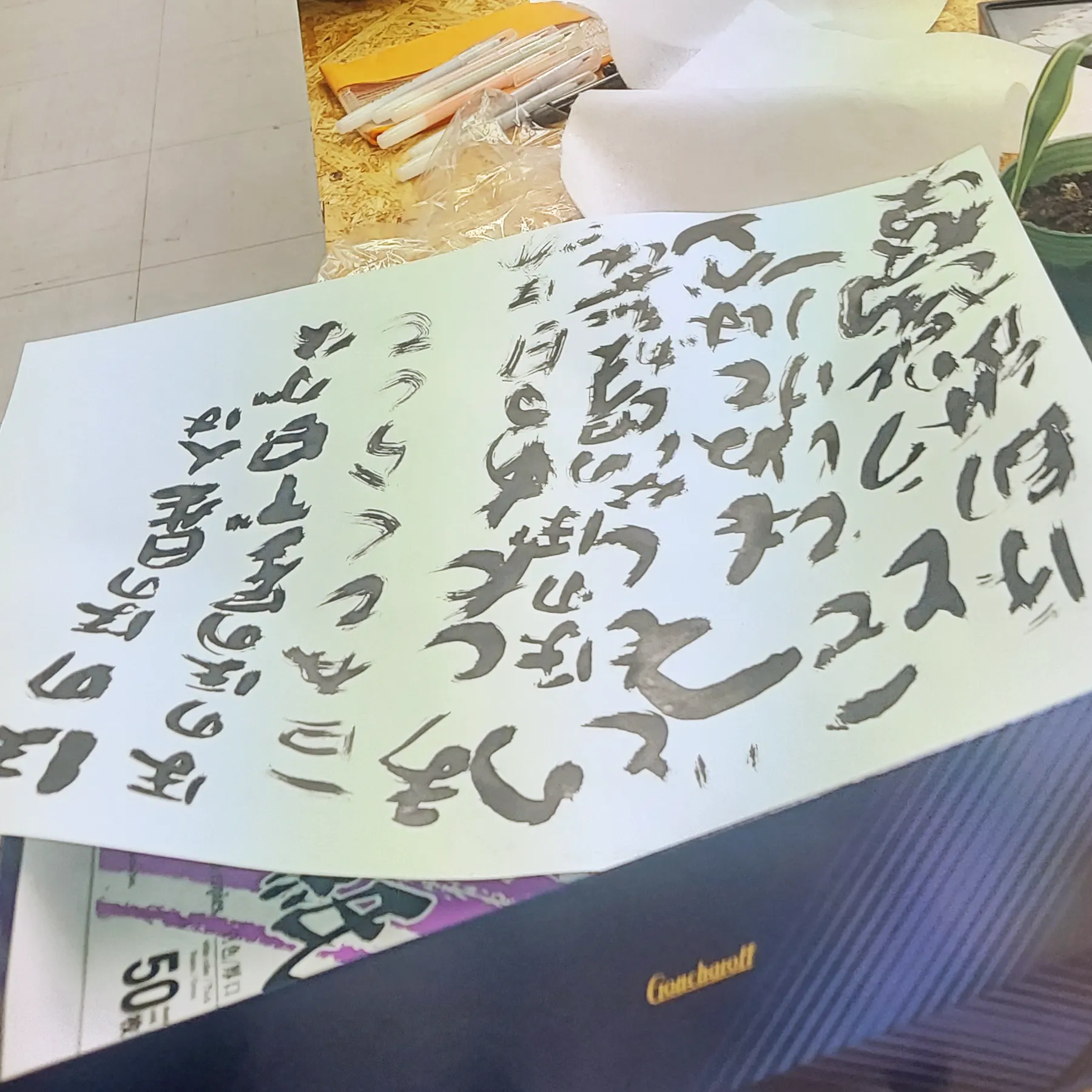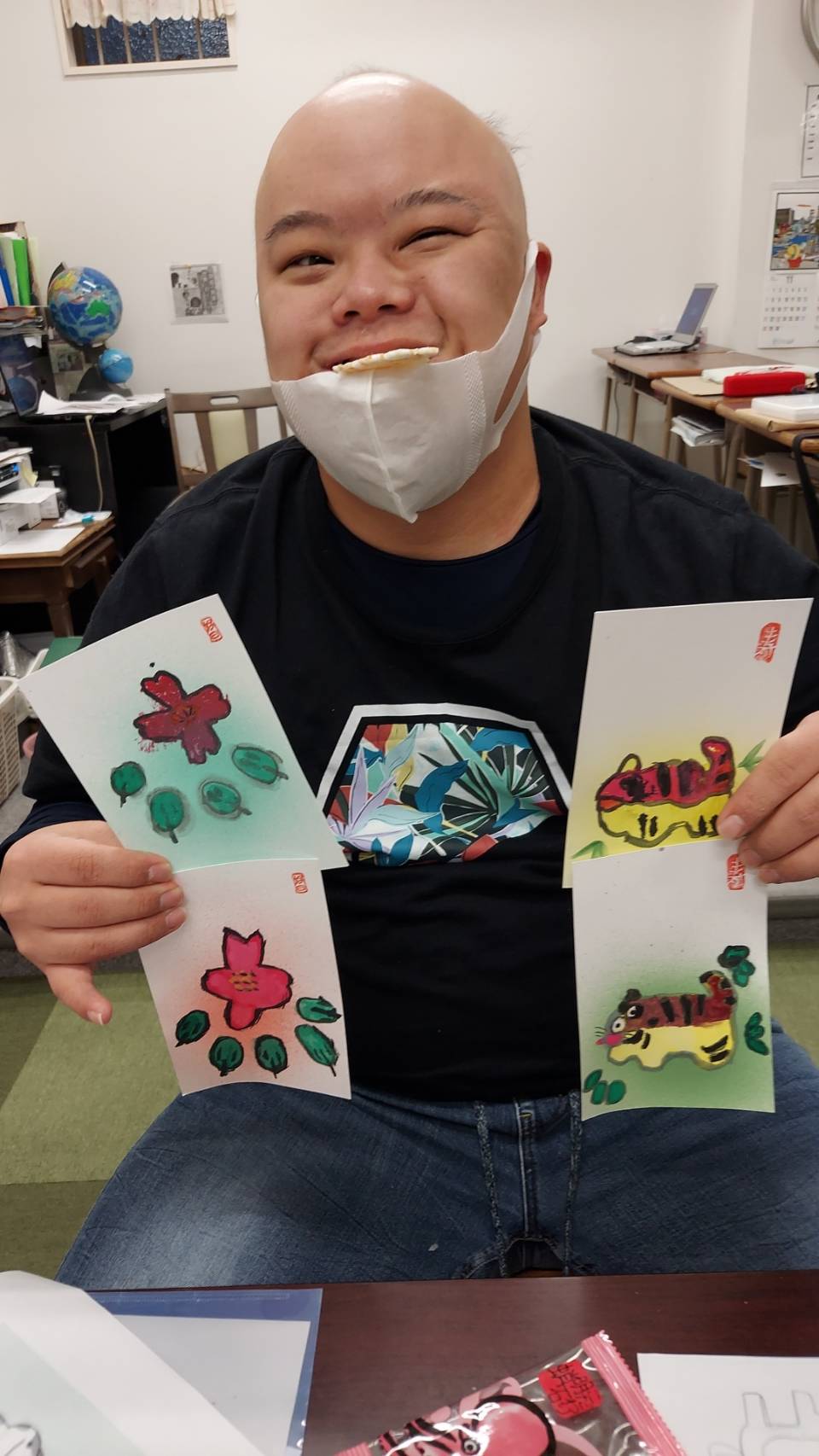笑顔~笑顔 仲間たちの仕事
いろいろな作業を無理せんと楽しくやってます
お仕事内容
清掃作業
- 市内のお寺(1か所)の庭の落ち葉の清掃
- ビルの廊下やトイレの清掃
室内での内職作業
- お菓子の包装袋のシール貼り
- 地域の情報紙「ぷらっと」のチラシ挟み込みおよびポスティング
- 市民会館のイベントパンフレット「しおさい」のチラシ挟み込みと封入
本松寺清掃
井戸水をかぶって猛暑対策

人丸ビル清掃
お掃除で気分もすっきり

情報紙「ぷらっと」
ポスティング!いいトレーニングです

ラベル貼り
明石名物たこせんべい
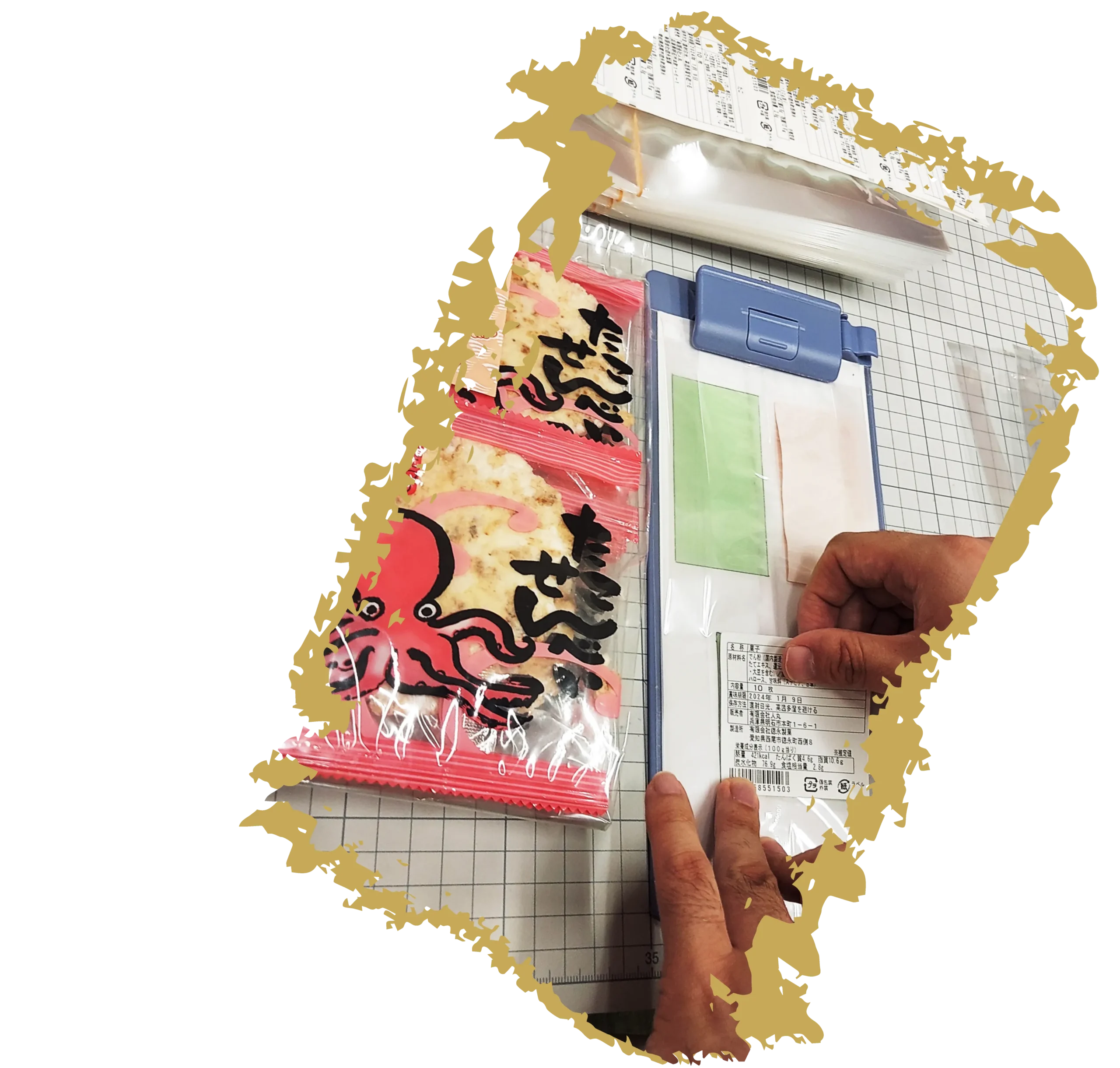

創造~自信 仲間たちの創作
お仕事内容
- 絵を創作したり、字をデザインしたり、仲間たちと立体作品を作ったり、様々なアートを仕事として楽しんでいます
- 美術イベントなどの会場イメージのインスタレーションやモニュメント創りなど、仲間たちの作品を活かしたアートを仕事にしています
- 演劇やダンスなどの舞台装置創りを請負って工賃を得ています

アートラボゆめのはこ

仲間たちの楽しみ

レクリエーション
毎月1回の楽しいイベント盛りだくさん
- 外食
- カラオケ大会
- お花見
- クリスマス会
など…